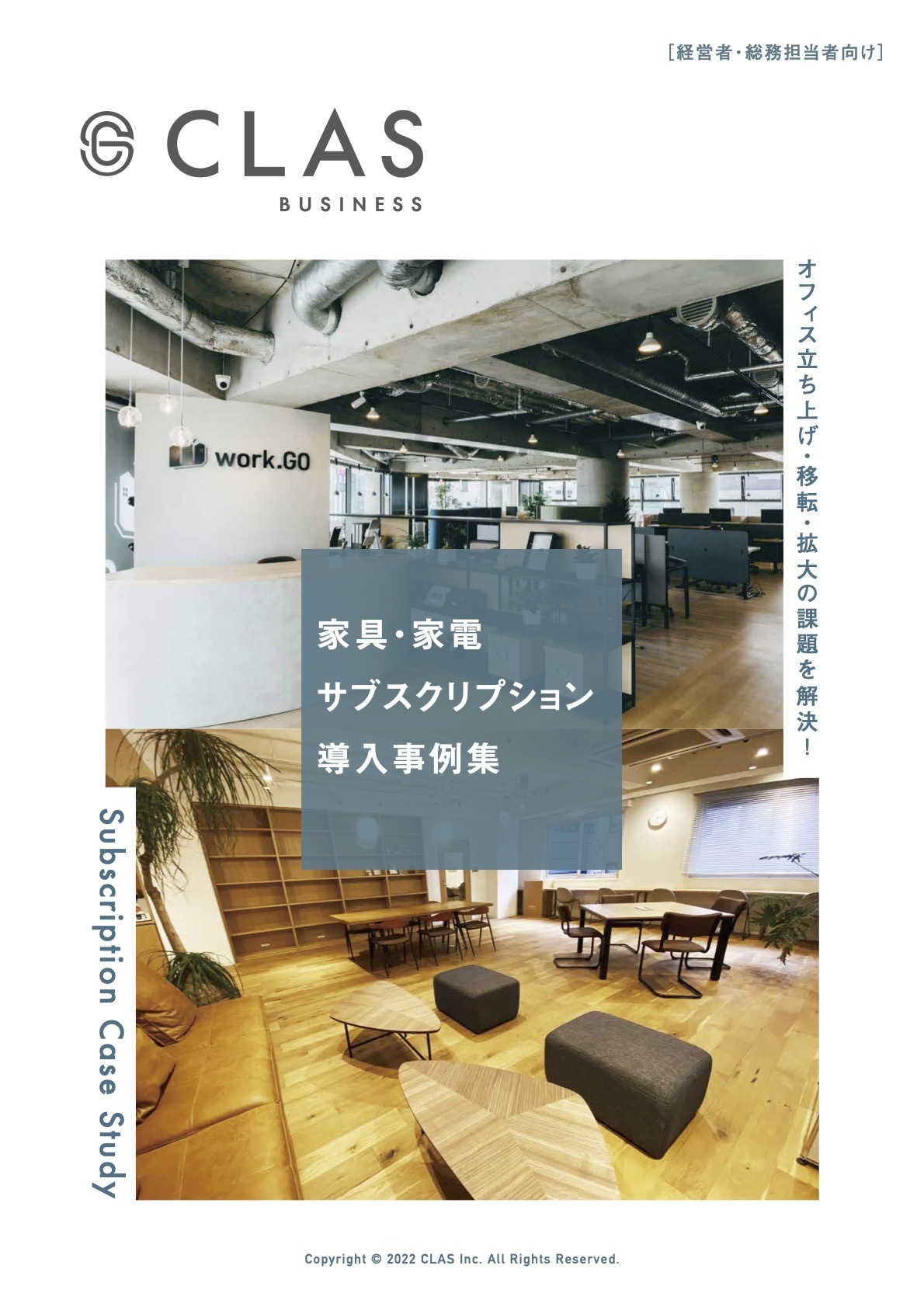-みずほ第一フィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 安原貴彦様、クラス代表取締役社長 久保裕丈のお二方から、簡単に事業内容についてご紹介いただけますでしょうか。
安原氏:私たちの会社は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーという名称で、1998年に設立されました。リスク管理やデリバティブのプライシングなど、数理工学を基盤とした業務を行っている会社です。
また、投資分野での年金基金や地域金融機関の運用ポートフォリオへの助言業務やデータアナリティクスやデータサイエンスの分野にも力を入れています。
金融機関以外の企業に対しても、経営管理やリスク管理のサービスを提供しており、最近では、ブロックチェーンや量子コンピュータといった先端技術の研究開発にも取り組んでいる会社です。
久保:私たちの業務としては、「借りる」「返せる」「買える」家具と家電のレンタル・サブスクサービス「CLAS(クラス)」を個人・法人向けに提供しているのですが、その根底には、購入や所有、廃棄に伴う大きな負担を軽減し、ユーザーに対して耐久消費財を自由に利用していただきたいという思いがあります。
このようにすることで、暮らし方や働き方を、時と場合に応じて最適化していただくことが、私たちの基本的な理念です。
したがって、できるだけ多くの耐久消費財を取り扱い、柔軟なプライシングで提供することを目指しています。
しかし、実のところ、これらのオペレーションや管理はかなり複雑です。このため、循環型事業として、裏側からデジタルトランスフォーメーション(DX)を進め、しっかりとオペレーションを支えるインフラ企業であることも強調できると考えています。
-クラスのサービスを選択していただいた理由についてお伺いします。まず、御社が直面していた課題や、オフィスを構える中での必要性についてどのようにお考えでしょうか。特に、オフィスに投資する意義や機能の重要性について、どのようにお感じになっていたのか、その背景をお聞かせください。
安原氏:コロナを経て、働き方が大きく変化したと感じています。コロナ禍の際、私たちはオフィスを大幅に縮小し、ワンフロアに機能の集約をしました。
現在の出社率は約3-4割程度で推移していますが、社員数は増加傾向にあり、全員が出社した際にはスペースが不足する状況にもなったため、フロアの増設をすることにしました。しかし、通常の状況では、エンジニアは自宅で集中して仕事をする傾向が強まり、オフィスにはあまり来なくなったんですね。
この結果、若手の教育やコミュニケーションを通じて新しいアイデアが生まれる機会が減少していると感じたのです。
我々は「サイエンスとインサイトで未来を照らす」というミッションを掲げていますが、サイエンスは磨かれる一方で、インサイトを生み出すもう一段の工夫が必要だなと感じたのです。
そのため、ひとつのフロアをサイエンス、もうひとつのフロアをインサイトのためのフロアとして、設計することにしました。
コミュニケーションが円滑に行える環境を整え、インサイトが生まれるオフィスを目指そう。そのために、さまざまな企業や家具メーカーを通じて、新しい働き方に適した什器を導入したいと考えていたことが背景にありました。
このようにオフィスのコンセプトが明確になってきたことに加え、オフィスの設計が生産性や従業員のエンゲージメントに与える影響についても多くの研究が行われていることも分かってきました。そこで、自社のオフィス環境を見直すだけでなく、実際にその環境を活用して実験を行い、どのように生産性が向上するかを探求したいと考えたのが、今回御社との関係を築くきっかけとなりました。
-インサイトの発見に関するお話がありましたが、コミュニケーションから生まれるインサイトの発見や、期待されるコミュニケーションのスタイル、さらには空間の利用方法について、具体的にお伺いできればと思います。
安原氏:コロナ以前では、全員が出社しており、皆が同じ空間で働いていました。
そのため、同じ部署のメンバー同士のコミュニケーションは非常に密接であり、朝から晩まで一緒に過ごすことで、相当な交流があったと考えられます。
しかし、コロナ後は出社率が下がり、フリーアドレス制度が導入されたこともあり、新たなコミュニケーションを模索する必要が生じました。
逆にそれは部署を超えた交流であったり、場合によってはお客様とのコミュニケーションであったり、より多様なつながりを築くことが可能な環境が作り出せると考えたのです。
当社には多様な技術が存在しますが、部門ごとに技術の違いがあります。そのため、異なる技術者同士が偶然に会話を交わすことが出来ないかということです。例えば、オフィス内でのちょっとした接点から、技術に関する意見交換に発展する可能性を追求したいと考えたわけです。
例えば、もしその技術があるならば、自分の取り組んでいることと組み合わせることで、新たなインサイトが生まれる可能性があると考えています。このような偶発的なコミュニケーションが実現できるような空間作りを考えています。
まだ始まったばかりですが、そのためにこのフロアを整備しているところです。

-もちろん、理想的な姿や先ほどの欧米企業の事例について、研究があることは承知していますが、先進的な取り組みを行っている企業の事例も少ないように感じています。そのような状況の中で、安原様が参考にされたケースや、周囲でそのような話を聞いた方はいらっしゃいますか。
安原氏:取引先で、先進的な取り組みを行なっている会社がありまして、実際にオフィスを拝見させていただきました。
オフィスデザイナーの方がいらっしゃって、その方にコンセプトについて詳しく伺いました。緑を配置することによって、リラックスした気分になることや、香りについてもお話を伺いました。
また、床の色も優しいトーンにしないと、落ち着いた雰囲気で仕事をするのが難しいといったことを教えていただきました。
リラックスできるゾーンや、集中するためのゾーン分けについて伺ったところ、色の選定が非常に徹底しているとのことでした。
その背景には、さまざまな分析が行われていると思われますが、生産性の向上に関する具体的な情報は特にありませんでした。
私たちはデータ分析を行っている会社のため、同様の分析を試みたいと思っております。
ー デザインのベンチマークについてお話しされていることを伺いました。家具は一般的にハードな要素を持つものですが、特に生産性の可視化やコミュニケーションの仕組みなどに関して、どのようなアイデアやアプローチを考えられているのでしょうか。
安原氏:最初にゾーンの区分を検討しました。
クリエイティブゾーンを設け、その隣にディスカッションゾーンを配置し、壁一面をホワイトボードにしました。また、その左側にはコラボレーションゾーンをつくりました。
実際の使われ方ですが、エンジニアが壁際で作業している様子を想像してください。彼が振り返ると、御社のホワイトボード付きテーブルがおいてあり、そこで、彼はテーブル上のホワイトボードにメモを取りながらディスカッションを行い、「これで進めましょう」と打ち合わせした後、再び開発作業に戻るという流れです。このような作業エリアをイメージしてゾーン分けをしました。
次に、外部の方々にも参加していただくことを考えています。例えば、みずほ銀行の方がユーザーであれば、その方にお越しいただき、3時間ほど集中して議論をしませんか、といったことをやりたいですね。
しかし、その際に外部の方をどのように識別するかという課題もあり、何らかの表示を設けることを検討しています。
ゾーンを表す表示盤を吊るすことで、社員の意識に「ここはこういうゾーンである」という意識が生まれ、利用方法が変化していくといった研究もあります。次の課題としては、実際に使用されているかどうか、またはそこで創出されたものが何であるかといった観点が挙げられます。
その可視化の方法について、まだディスカッションベースではありますが、例えばカメラを設置したり、音声データを取得することが考えられます。しかし、どの情報を収集すれば、オフィスの利用状況と生産性を正確に測定できるのか、悩んでいるところです。
エンゲージメントが向上したり、インサイトが生まれる瞬間には、人々の動きが速くなる傾向があるのではないかと推測しています。
「面白いね」や「それは良いね」といったやりとりは、声のトーンも変わりそうです。このような要素を測定することで、インサイトが生まれている瞬間を測定出来ないか検討していきたいですね。部門を超えたコミュニケーションの重要性が再認識されることもあるでしょう。
部内の会議においては、部長のみの発言で進行するような、一方通行の形式では、どうしても緊張感が欠けてしまいますね。
しかし、双方向のコミュニケーションが行われると、身振りや手振りが加わり、声のトーンも上がり、活気を感じることができるでしょう。
このようなデータを蓄積して活用し、効率的な働き方を実現する企業のモデルをお客様に提案したいと考えております。
そして、可能であれば御社と共に取り組んでいきたいと思っております。
-クラスのサービスが、他社様と比べ、どのような点で優位性を持つのか、ぜひお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。

安原氏:まず、やはりサブスクリプションサービスが適切に運営されていることではないでしょうか。
別のサブスクリプションサービスでは、違約金や解約金が発生するなど、サブスクリプションとは言えないサービスもあるようです。
一方で、クラスさんの最大の魅力は、真のサブスクリプションサービスを提供している点にあります。返却された家具はどのように扱うのかと私が質問したところ、クラスさんは家具を整備して別のお客様に再提供するとのことでした。
非常に共感を感じましたし、さまざまな家具を試してみたいという思いにつながりました。
また、ここにあるプライベートブランドのように、ある意味、家具の実験も行われていますね。
ここにホワイトボードがあるということは、確かにそう言われれば納得できる部分もありますが、なかなか思いつきません。その点が既存のメーカーとは大きく異なると感じています。
そして、何よりも久保さんのサーキュラーエコノミーを作りたいという強い志がありました。この思いに惹かれたのが一番ですね。
久保:ありがとうございます。確かに、その通りです。
多くの家具メーカーは、素晴らしい事例やこれまでの知見、ノウハウを蓄積しています。その中からお客様の要望をしっかりと把握し、具体的な形にしていく取り組みを行っていることは、非常に素晴らしいことだと考えています。
私自身も、経営者としての立場から、またコンサルタントとしての経験から言えることですが、クライアントの課題や要望を伺いながら、ある程度アレンジを加えつつ最終的な提案をしています。
しかし、その課題は時期によって変化することがあります。特にコロナ禍の真っ只中や、現在のように国内外の大手IT企業などがオフィスに戻りつつある状況では、課題感自体が異なることは明らかです。
そのため、課題が異なれば理想像もまた変わるというのが、私が経営者として常に感じていました。単に内装を一新してそれで完了というわけではないんですね。
私は、オフィスの在り方は常に変化していくべきであり、一度納品されたからといって、それが直ちに最適な状態になるとは考えていません。
やはり、安原様がおっしゃっていた中で、特に感銘を受けたのは、人々の動きや働き方に関して、まだ十分な計測手段が整っていないという現状のなかで、これを構築しようとしている取り組まれていることです。これはぜひ、一緒に取り組ませていただきたいと強く思っております。
安原氏:どの程度の成果を上げられるか、これから挑戦していくところですね。
やはりオフィス業界やデータ分析の分野において、それを適切に可視化できるツールが整備されれば、状況は大きく変わるのではないかと考えています。
久保:私たちのサービスを利用していただいているお客様の中には、サブスクリプション形式でありながらも、固定的な利用に移行する方もいらっしゃいます。
多くの方々は、資金面や人的コストに対する負担を避けたいと考えがちですが、安原様の考え方は、特に、働く人々の意見を収集する必要性について重要視されています。
一定の人的コストは避けられませんが、その結果として生産性やクリエイティビティが向上すれば、そのコストは回収できるという確信を、多くの事例から実感しているのでしょうか。
安原氏:事例からの考察ではありませんが、当社はデータサイエンティストが多く在籍しているため、その中には行動科学に関する研究を行っている者もいます。彼らから、このような取り組みを進めたいといった声もありました。
さまざまな場所で同様の取り組みが行われていると思いますが、まだ十分には進んでいないのが現状です。
しかし、現在は、コロナ禍も終息し、オフィス環境が急激に変化しています。また、人的資本経営が重要視されており、人的資本の活性化が求められています。これは生産性の向上に直結する要素であると考えていますが、そのためにはエンゲージメントの向上が不可欠ですし、今まさにそのような時代に突入しているのではないかと感じています。
そして、人的資本経営を考える際には、オフィス環境も重要であると認識しています。

久保:確かに人的資本経営が注目されている中で、どの企業もその重要性を訴えています。
しかし、具体的にどのような施策を講じ、どのように行動に移しているのかを考えている企業は、まだ少ないのかもしれません。エンゲージメント調査を実施し、その結果に一喜一憂しているだけでは不十分です。
少し余談になりますが、実は今日ここに来る直前まで、東京大学の教授とお話ししておりました。現在、私たちは東京大学との共同研究を進めており、その内容は循環型事業が環境に与える影響や、ユーザーの態度変容に関するもので、主に消費者向けの視点から研究を行っています。その文脈において、循環型事業と人的資本経営の相互作用についての研究は、非常に興味深いテーマであると思いました。
さらに話が逸れますが、サステナビリティの観点からESGについて触れたいと思います。Gはガバナンスですので、その点は置いておくとして、環境に配慮したビジネスを展開することが重要ですよね。そして、人的資本に関する部分はSに該当し、これらは両立させる必要があると考えています。私たちのメンバーも、このテーマに非常に関心をもっております。
オフィスの在り方を考える際に、私たちの事業の一つとして興味深い点は、アカデミックな方々との対話において、基本的には一つのフレームワークの中に留まる傾向があるということです。これは、過去に蓄積されたデータを基に分析をする必要があるため、当然のことと言えます。
しかし、私たちは様々なテストを行う中で、最適な地点から意図的に大きく外れたアプローチをとることができます。オフィスの在り方についても、特異点を目指して新たな試みを行うことが、一つの挑戦として有意義かもしれません。
特異点に挑戦し、たとえばそのプライシングが通用しないケースがあったとしても、これが人気を博すことがあります。アカデミックな観点からは予想できないことですが、そうした現象が現れることについて、考えさせられる部分があると感じました。
そういう特異点を探しながら、新たな流れを創出していく過程に、当社のサービスを活用していただけると幸いです。
-現在検討している事項や取り組みを進めるために、よりクラスに期待していることはありますか。
安原氏:理想的には、久保さんが仰ったように、このステージにある企業にはこのような家具が最も適しているとか、特定の課題を抱えている企業にはこのようなオフィスと家具を導入することで解決できるという提案を、データに基づいて提供できるようになると非常に良いですね。
最初にお話しした際、スタートアップは急速に成長するため、このようなサブスクリプションモデルが最適であるとおっしゃっていました。
私もその通りだと思います。スタートアップの成長過程は、2、3人から始まり、20人、50人と増加し、やがて上場を考える段階に入ります。
このような成長段階において、どのような家具が適しているか、また、従業員数が100人、200人に達した際にはどのようなアプローチが有効かを提案できることが重要ですし、この家具を使用した場合、生産性が向上したという具体的なデータを提供できれば、非常に価値のある情報となるでしょう。
久保:おっしゃる通りです。何らかのプロンプトがあれば、適切な提案を行うことが可能です。もちろん、カスタマイズは行いますが、まずはこのカテゴリーでやりましょうといった提案ができますね。
安原様のように先を見据えた考え方を持ち、さらに実行にうつされている方は、少ないと思います。
他のプレイヤーを見渡すと、総務の担当者としては、物事を変えることに対して消極的であり、空間を変えること自体が面倒に感じられることが多いようです。
しかし、御社に関しては、そうした状況を超えて、実験を行う意欲までありますね。その行為の評価や意義、興味深さについて広めるために、ぜひご自身の考えを共有していただけると幸いです。
安原氏:私は人的資本経営の観点からこの事柄を捉えています。人が活性化し、質の高い仕事を行うことで、従業員も幸福感を得られ、企業の生産性が向上し、業績も向上していく。
その観点から、オフィスは非常に重要な要素であると考えています。コロナ禍における在宅勤務やリモートワークを経て、先進的な欧米企業はその重要性に気づき、すでに実行に移しています。
しかし日本人は、事実を突きつけないと行動に移しにくい傾向がありそうです。データを通じてその重要性を示していきたいです。
当社の役割は、お客様にそのような情報を提供することだと考えています。
久保:なるほど、御社のような業態の方々が成長を遂げることができれば、それは日本全体の生産性向上にもつながりますね。
安原氏:さまざまな事柄に取り組む必要があります。それに加えて、データの活用やオフィス環境やエンゲージメントの向上も同様に重要であり、あらゆる人的資本に関する要素を考慮する必要があります。
-銀行や金融機関には、依然として保守的なイメージが強く残っています。事業投資においては先進的な取り組みを行っている場合もありますが、全体としては保守的な傾向が色濃く見受けられます。その中で、どのようにして先進的な考え方にシフトすることができたのでしょうか。
安原氏:やはりエンジニアが多いからでしょうか。エンジニアの方々は自宅での勤務を好む傾向があります。
この点については、生産性を向上させるのであれば、その選択を支持したいと思います。
しかし、このような人々が、このオフィスなら少し訪れても良いかもしれないと思うかもしれません。
そして実際に出てみると、久しぶりに会った人と再会し、「最近はどうしているの?」といった会話が交わされ、「実は今、これをやっているんだ」と話し、「それについて今度教えてほしい」と続くのです。
そのあとはオンラインミーティングでも全く問題ありません。「次回、一緒にコラボレーションしましょう」といった流れにつながるきっかけ作りを、エンジニアの会社だからこそ実現する必要があると考えています。
久保:なるほど、例えば久しぶりに会社に顔を出してみるというのは、何かしらのきっかけがあれば良いのではないでしょうか。
我々のお客様のシェアオフィスでは、そこで働く方々が主催するイベントが行われることがありますが、そういった試みについてはいかがでしょうか。
例えば、オフィスへの出社を促進するためのきっかけを提供する、ある意味で無形の商材に関連するものについて、何らかの形でサポートできれば良いのではないかと思いました。
安原氏:例えば、先々週から先週にかけて、200人を4つのグループに分け、夜に2回、昼に2回のミーティングを行いました。
そこではテーブルを円形に配置し、約50人程度が集まる形にしました。私が中央に位置し、皆さんから意見を伺い、どのようにすれば会社でのリアルなコミュニケーションが活性化されるかを話し合いました。
皆さんにとっては月に一度のイベントでも構いませんし、例えば夕方の3時頃に訪れると、会社がお茶を提供してくれたり、その他のサービスがあればといった意見がでました。
また、エンジニアとしては研究発表の機会もあるといいですねという意見もありました。
久保:そうですね、そういったイベント用の什器についてですが、たとえばビールサーバーがあったりしたら、みなさん喜ばれるかもしれません。
会社に集まるようなイベントを実施するために、必要な要素がいくつか考えられます。それは物品であったり、場の提供であったりします。
当社としては、まだ具体的なサービスには至っておりませんが、集まりのきっかけを作るための準備を、お手伝いできれば面白いのではないかと考えています。
安原氏:それはかなりの範囲で横展開することができそうですね。
予算を伝えて、その範囲内で調整をする。総務の負担を軽くするようなサービスいうものができるかもしれません。これからも、さまざまな取り組みを御社と進め、知見を集めたいと思っております。